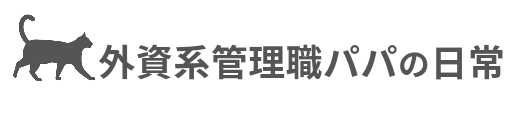サンスーシ宮殿は、18世紀のロココ様式の優雅さを備えつつもこじんまりとした控えめ感があり、この宮殿を建設させたフリードリヒ2世の趣味の良さが際立っていて、一見の価値ありです。ベルリンから日帰りで観光可能です。
サンスーシ宮殿(Schloss Sanssouci)は、首都ベルリンにほど近いブランデンブルク州ポツダム市にある宮殿です。プロイセン王国の王だったフリードリヒ2世が夏の間の居所として建設させたもので、わずか2年の建築期間で1747年に完成しました。
サンスーシ宮殿の内装は花や植物の葉、貝殻などをモチーフにした優雅な曲線のデザインに加え、金細工を多く使った装飾を多用するなど、当時のヨーロッパ宮廷建築で流行していた「ロココ様式」の代表的な建築物として知られています。周辺の宮殿や庭園と合わせて「ポツダムとベルリンの宮殿群と公園群」として、1990年に世界遺産に登録されています。
なお、サンスーシ(Sanssouci)はフランス語で「憂いなし」という意味で、日本語では「無憂宮」と呼ばれることもありますが、この記事ではサンスーシ宮殿の呼称で統一します。
以下、この記事で紹介するサンスーシ宮殿や庭園についての説明は、主に筆者が現地を見学した際の音声ガイドの内容および、サンスーシ宮殿公式アプリにおける施設紹介の内容を参照しています。