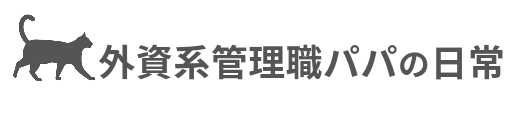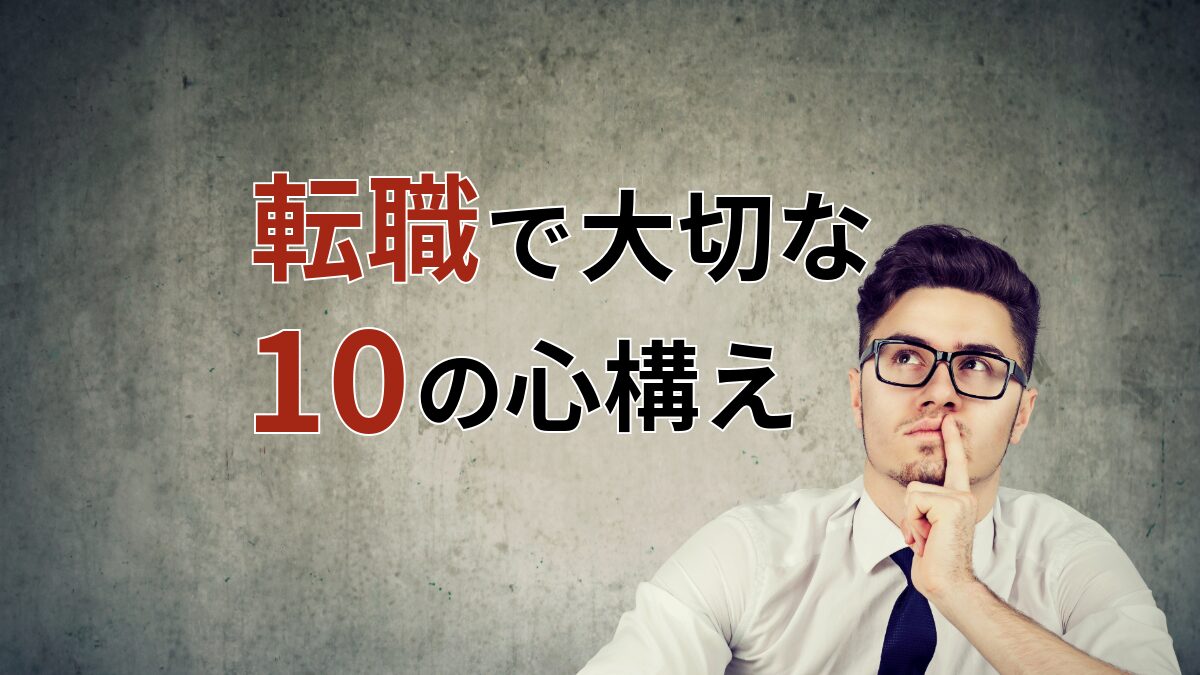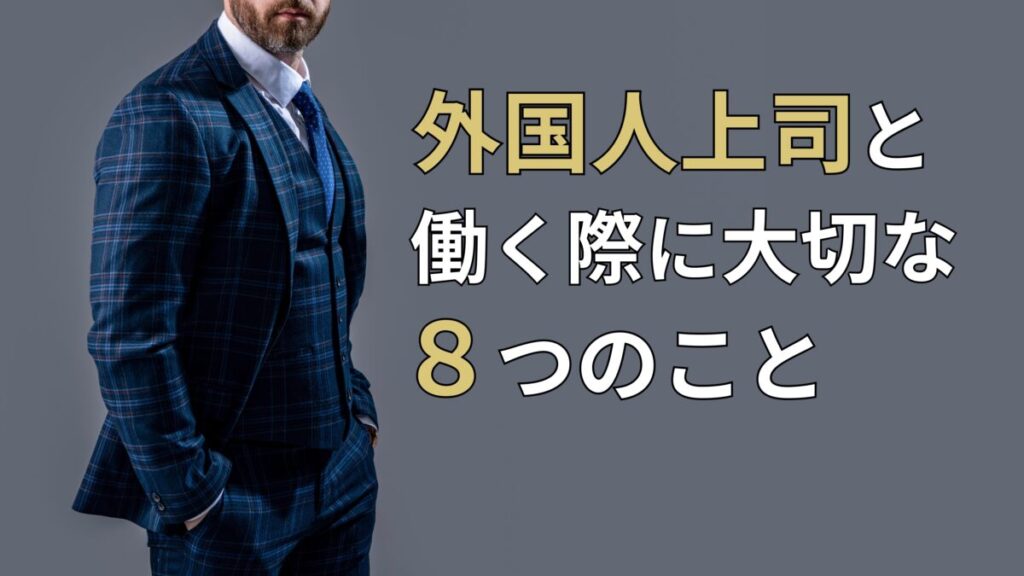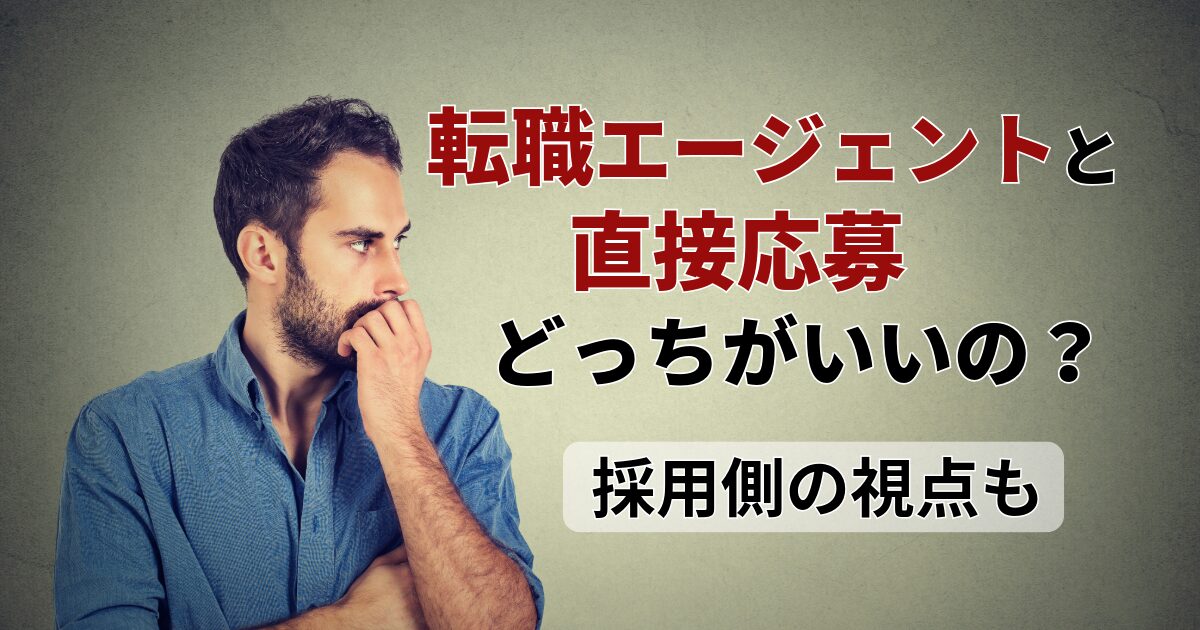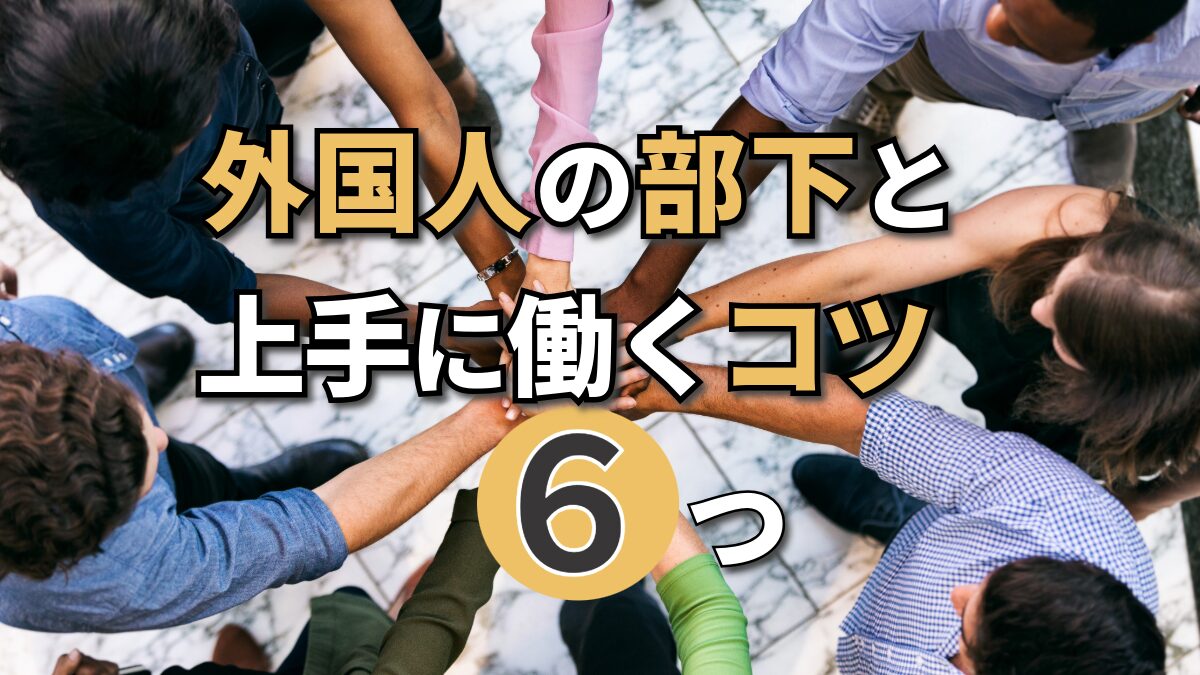今日は転職における心構えと重要なポイントについて語ります。
みなさん、仕事は好きですか?充実していますか?もちろん仕事で達成感や満足感を得る場面もあると思いますが、多くの人は何らかの不満をかかえていて、すでに転職活動中の方もたくさんいると思います。私も今まで外資系・日系含めて5回の転職をしており、その全てで年収アップに成功しています。また業務においてはチームリーダーとしてメンバーの採用にも責任を負っており、国内外で多くのメンバーを採用してきました。
ここでは私のこれまでの経験から、転職において重要な心構えやポイントについて紹介します。
在職中に転職先を決める


最も基本的なことですが、現職の仕事や環境にどれだけ不満があっても、できる限り在職中に次の仕事を決めるようにした方が良いです。理由は次の3点です。
- 離職中だと条件面で転職先に足元を見られる
- 応募者が既に離職中の場合、採用側から見ても「この人はすぐに仕事を見つけたいだろうから、ある程度低い条件(前職を下回る条件)でも来てくれるだろう」と思われがちです。結果として、同じようなスキル・経験を持った人材であったとしても、在職中の場合と比べて低めのオファー条件を設定されるリスクがあります。
これに対して在職中の場合、本人にとって満足できる条件でなければ現職に留まるという選択肢もあるため、採用側の視点でも「現職を上回る条件を出さなければ来てくれないだろう」という考えが働き、結果として離職後の場合よりも良い条件になる可能性があります。
- 応募者が既に離職中の場合、採用側から見ても「この人はすぐに仕事を見つけたいだろうから、ある程度低い条件(前職を下回る条件)でも来てくれるだろう」と思われがちです。結果として、同じようなスキル・経験を持った人材であったとしても、在職中の場合と比べて低めのオファー条件を設定されるリスクがあります。
- 離職中の応募者を避ける企業もある
- 会社や採用責任者の方針によって異なりますが、中には在職中の応募者のみを事実上の選考対象とし、離職中の求職者は書類選考で落とすようにしている場合もあります(もちろん求人情報には「在職中のみ応募可」などは記載していませんが)。
私のこれまでの経験でも、あるポジションの採用活動を始める際の人事との打ち合わせで、「離職中の応募者も選考対象としますか?」と確認されたことが何度もあります。私自身は応募者が離職中であっても気にせず選考対象としていますが、人事としては「在職中に次を決めずに辞めた人は計画性が無い」、または「何か問題があって次を探す間もなく辞めざるを得なかった可能性もある」と考えるようです。
- 会社や採用責任者の方針によって異なりますが、中には在職中の応募者のみを事実上の選考対象とし、離職中の求職者は書類選考で落とすようにしている場合もあります(もちろん求人情報には「在職中のみ応募可」などは記載していませんが)。
- 離職中だと気持ちに余裕がなくなる
- すでに仕事を辞めて転職先を探している場合、一般的には少しでも早く無職状態を抜け出したいという考えが働くのではないでしょうか。それによって気持ちに余裕がなくなり、在職中だったら検討対象にもならなかった企業に応募してしまったり、提示されたオファーがイマイチだったとしても「これを逃せば次はないかも」との恐れから不本意なオファーを受諾してしまいがちです。結果として転職後もすぐに不満が噴出し、また早期離職をするという悪循環につながるリスクも。
すぐに転職予定がなくても転職サイトやエージェントに登録


今すぐに転職する予定がなくても、転職サイトに登録したり、転職エージェントと接触してマーケット情報をシェアしてもらった方が良いです。目的は「自分の市場価値を知るため」と「転職マーケット情報の収集」です。
- 自分の市場価値を知るため
- 転職サイトに登録すると、たくさんの転職エージェントや企業から求人の案内(スカウトメール等)が来ます。それらに記載されているポジションの想定年収や職位をざっと見ることで、もし自分が転職活動をした際に、どの程度のレベルのポジションが現実的に候補として検討できるのか、おおまかに想像できると思います。
もし現職の条件を下回るような案内しか来ない場合は、自分の市場価値に対して現職の条件が優れているということですから、現職に留まった方が良いという判断もできます。
- 転職サイトに登録すると、たくさんの転職エージェントや企業から求人の案内(スカウトメール等)が来ます。それらに記載されているポジションの想定年収や職位をざっと見ることで、もし自分が転職活動をした際に、どの程度のレベルのポジションが現実的に候補として検討できるのか、おおまかに想像できると思います。
- 転職マーケット情報の収集
- 定期的に転職サイトを見たり転職エージェントと情報交換をすることで、自分の職種や業界における転職のトレンドや、どのようなポジションに需要があるかが見えてくるようになります。もし自分のスキル・経験を必要とするようなポジションが増えている状況であれば、「その気になればいつでも次を探せる」という余裕をもって現職に取り組むことができるようになります。
外資系企業や日系大手への転職を考えるのであれば、とりあえずLinkedInと
転職の目的を明確にする


なぜ転職をしたいのか、その理由と目的を自分の中で明確にしましょう。世の中に無数の求人がある中で、自分の「ゆずれない軸」を持っていれば、本来の目的からずれた案件に応募することによる時間の浪費を避けられます。
転職理由は面接で伝える「外向きの理由」と自分の中の「内向きの(本当の)理由」がありますが、ここでは後者を指しています。例えば「年収を上げたい」が転職理由であれば、現職を下回る待遇の案件には最初から応募しない、あるいは選考初期の段階で大まかな想定年収を先方にそれとなく確認し、希望以下であればその時点で辞退すべきです。
転職の理由が「ワークライフバンスを重視したい」であれば、受け入れ可能な最低年収ラインを設定したうえで、あとは「残業ゼロ(または残業〇h以下)」や「転勤なし」などをアピールしている求人を中心に検討した方が良いです。
現職より上の給与を目指す


特別な事情がない限り(転職理由がワークライフバランス重視で年収度外視など)、転職にあたっては現職よりも上の給与を目指した方が良いです。海外では基本的に定期昇給がほとんど無いことが多いので、転職を重ねて給与とポジションのランクを上げていくの一般的ですし、日本にある外資系企業でキャリアを作っていく場合も、おおむね同じ考えが当てはまります。
また日系企業間の転職であっても、転職の際に着実に給与アップを達成してきている人は、採用側から見てもポジティブな印象を持たれることが多いです。
基本給が大事
転職先の想定年収が1,000万円だとした場合、その内訳をよく確認しましょう。その金額がボーナスや各種手当を除いた基本給(ベース給)だけでその額の場合と、基本給は700万円で標準的なボーナス額300万円を加えて合計1,000万円の場合では、全く別物です。当然前者の方が保証されている金額が多いという点で優れていますし、将来別の会社に転職する際の給与交渉でも有利です。
一般的には前職給与の10%アップ程度をベンチマークとして交渉することが多いですが、そのベースとなる「前職給与」が基本給だけで1,000万円であれば堂々と1,100万円以上を希望として出せるのに対し、基本給700万+ボーナス300万の場合は、先方から値切られる可能性があります。
\ 外資系・ハイクラス求人多数 /
残業時間は定時をベースに確認


ほとんどの人にとって、残業はできるだけ少ない方が良いでしょう。面接の中で所属予定部署の平均残業時間について確認することがあると思いますが、その際にはその会社の標準労働時間が何時間なのかを考慮する必要があります。
例えば以下のような2社があるとします。
- A社:残業時間10h/月、定時は9:00 – 18:00 (休憩1時間)で標準労働時間は8時間/日
- B社:残業時間20h/月、定時は9:00 – 17:00 (休憩1時間)で標準労働時間は7時間/日
この例では一見すると残業時間が少ないA社の方が魅力的に思えますが、そもそもデフォルトの労働時間がB社に比べて毎日1時間も長いので、トータルではB社の方が労働時間が少ないことが分かります。
転職先の口コミを確認


応募先の企業がどのような社風やカルチャーを持っているのかは、とても重要です。ハラスメントや不正が横行している会社は論外ですが、そうでなくても「新卒プロパーが中心で中途採用は居心地が悪い」や「みんなやる気がなく退職者が続出」というような情報は、その会社に行くかどうかを判断するうえで重要だと思います。そのような情報は会社のホームページを見ても載っていませんし、転職エージェントも知らないことが多いです。
そこで、実際にその会社に所属している(していた)社員による口コミが投稿されているサイトを確認してみましょう。今や転職口コミサイトのチェックは必須です。下記のサイトでは、登録後48時間以内であれば各企業の上位口コミ10件が見放題なので、面接前に応募先の口コミをチェックしておきましょう。
違和感を感じたら辞退


選考途中で「ちょっと違う」という違和感を感じたら、ためらわずに辞退しても構いません。自分の直感を大事にしましょう。例えば面接日程の設定が毎回一方的だったり、こちらの質問に答えない、あるいは面接担当者の態度が横柄や失礼だったりする場合は要注意です。
特に直属の上司となるHiring Managerの態度が横柄だったり、何となく合わなそうな場合は、辞退を検討した方が良いです。仮にオファーが出たとしても、失礼だったり相性が悪い上司の下で働くのはストレスです。
オファーレターにサインするまで退職届は出さない
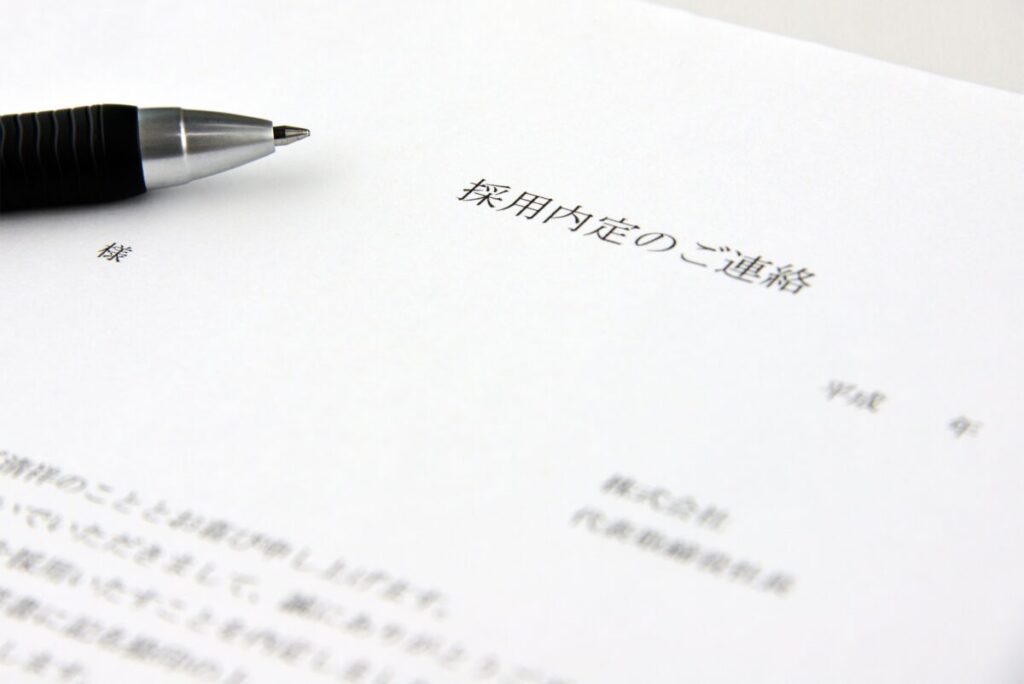
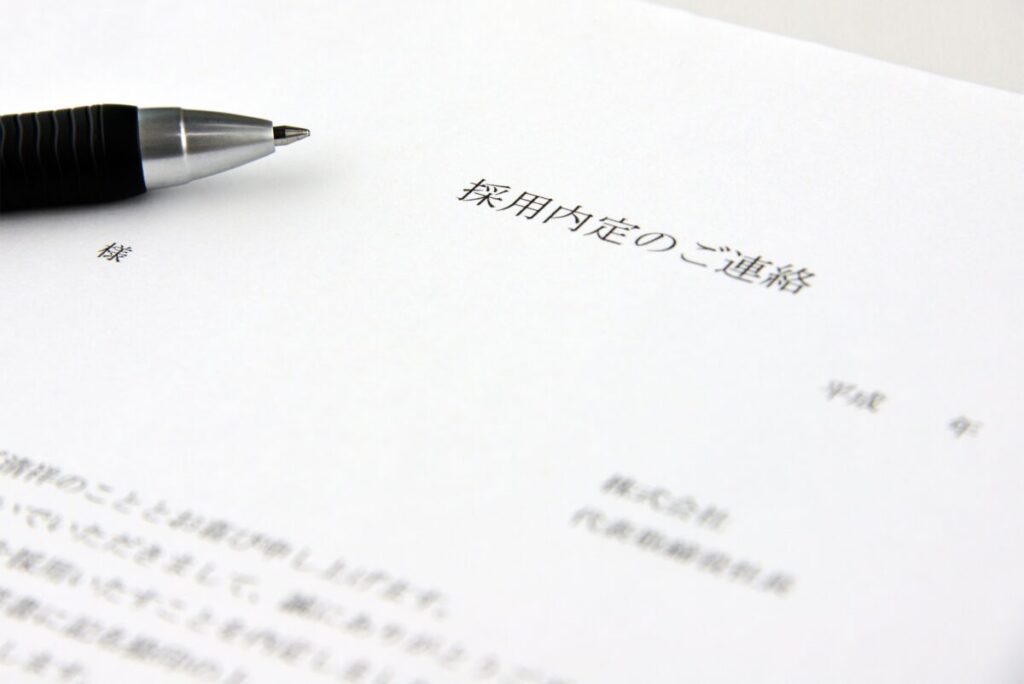
これも基本中の基本ですが、第一希望の会社から「内定を出す」と口頭で言われていても、正式なオファーレター(雇用条件通知書、雇用契約書など)にサインするまでは絶対に現職の退職届は出してはいけません。先方の人事が「内定を出す」と言っている以上、実際には社内でオファーを出すための手続きを進めているのは間違いありませんが、何らかの理由でオファーが承認されない可能性も残されています。
特に外資系の場合は、ポジションによっては本国の決裁が必要だったりして、よくわからない理由で最終承認が下りない可能性もあったりします。また、会社の業績の変化でいきなり採用フリーズがかかり、全ての採用が全世界的にストップされることもあります(私も採用側として経験があります)。
オファー条件は給与以外も大事
おめでとうございます。無事にオファーレターを貰いました。志望度が高かった企業であればすぐにサインしたくなる気持ちもわかりますし、エージェント経由で応募している場合は、早くサインするよう担当者が猛烈にプッシュしてくると思いますw
ただ少し待ってください。一般的にオファーレターには一週間程度の回答期限が設定されているので、サインする前に以下の点を確認し、疑問点をクリアにしましょう。
- 有給休暇
通常は有給休暇の付与条件が記載されていると思います。法定の最低日数を下回っていないことはもちろんですが、入社時点では最低限の日数だったとしても、毎年増えていくのか、その場合の条件についても確認した方が良いです。 - 各種手当
会社によっては住宅手当、家族手当、資格手当などが付与され、それが結構な金額の場合があります(特に日系の場合)。総支給額の相当部分を手当が占める場合、手当の金額や支給条件についても確認しましょう。 - 出張旅費
出張が多い仕事限定ですが、出張が全体の30%以上を占めるような場合、旅費や宿泊費のルールはどうなっているかも確認したいところです。特に最近はインバウンドの増加で国内ホテルの料金が高騰しているにもかかわらず、20年前の感覚で東京、名古屋、大阪で一泊1万円程度しか宿泊費を出さない会社の場合、かなり厳しい出張生活を強いられることになります。
また海外出張が多い仕事の場合、何時間以上のフライトだったらビジネスクラス(またはプレミアムエコノミー)が使えるのかも重要です。北米やヨーロッパに頻繁にエコノミーで出張するのは苦行です。
上記以外の点についても、疑問点があったらためらわずに先方の人事に確認した方が良いです。「こんなことを聞いたら失礼と思われないかな」と心配する必要はありません。正式なオファーレターが出ていて、相手はこちらに何としてもサインして欲しい状態です。立場としてはこちらが圧倒的に強いので、心配は無用です。
また、オファー回答期限の延長も交渉可能な場合がありますので、疑問点の確認に時間がかかりそうな場合は先方に相談してもよいでしょう。この手の交渉はエージェント経由の方がしやすいです。
まとめ
この記事では転職にあたって大切な心構えとポイント10点について紹介してきました。まとめると以下のとおりです。
- 現職を辞めるのは次の仕事を決めてから
- 自分の市場価値とマーケット理解のために転職サイト・エージェントに登録
- 転職の理由と目的を明確にする
- 可能な限り現職より給与アップを目指す
- 給与は基本給の部分が大事
- 残業時間は標準勤務時間をベースに確認
- 応募先企業の口コミを確認
- 選考途中で違和感を感じたら辞退してOK
- オファーレターにサインするまで退職届は出さない
- オファー条件の中で給与以外の条件も確認し、疑問点はためらわず人事に確認。
みなさんが転職活動をする際の参考になれば幸いです。
外資系や大手日系への転職を考える場合、転職サイトに登録して情報収集するのが一般的ですが、ビズリーチへの登録はもはや必須と言ってもよいでしょう。ハイクラス案件を扱うエージェントからどんどんスカウトが届きますし(的外れなスカウトは無視してOK)、企業から直接カジュアル面談などの依頼が来ることもあります。私の所にも毎日のように何かしらのメッセージが届いています。
\ 外資系・ハイクラス求人多数 /
外資系企業への転職を希望する場合、外資転職独自のノウハウやネットワークを持っている転職エージェントを使うと心強いです。
また、経理や人事、法務、総務など管理部門の転職も特化型エージェントが頼りになります。会計士や弁護士向け求人もたくさんあります。
経理財務・人事総務・法務の求人・転職なら|管理部門特化型エージェントNo.1【MS-Japan】当ブログでは、以下のとおり転職や仕事関連の記事がありますので、併せてご覧ください。